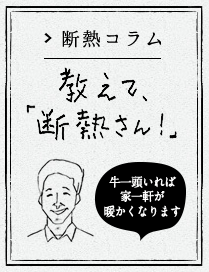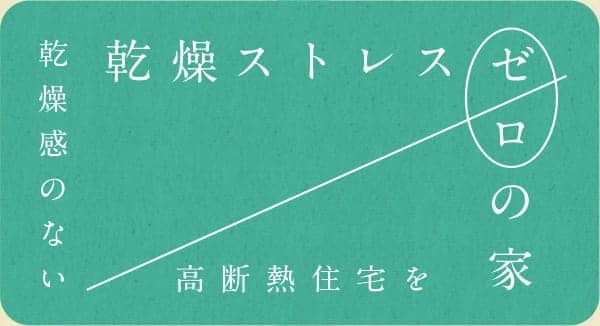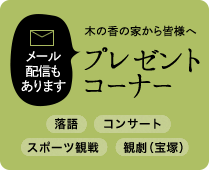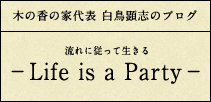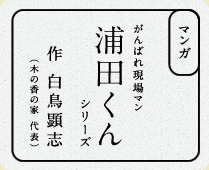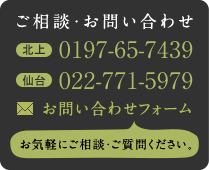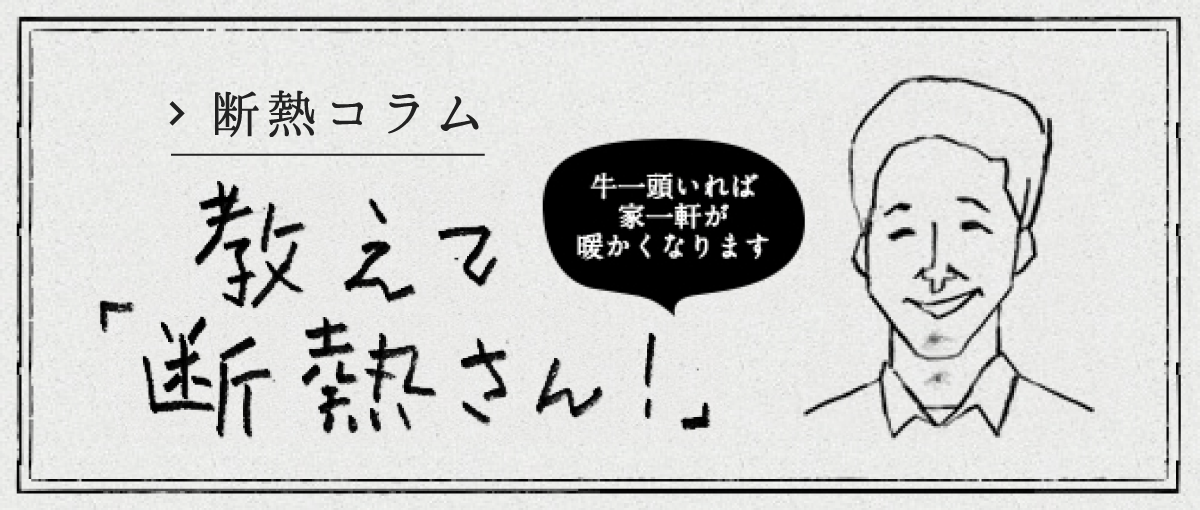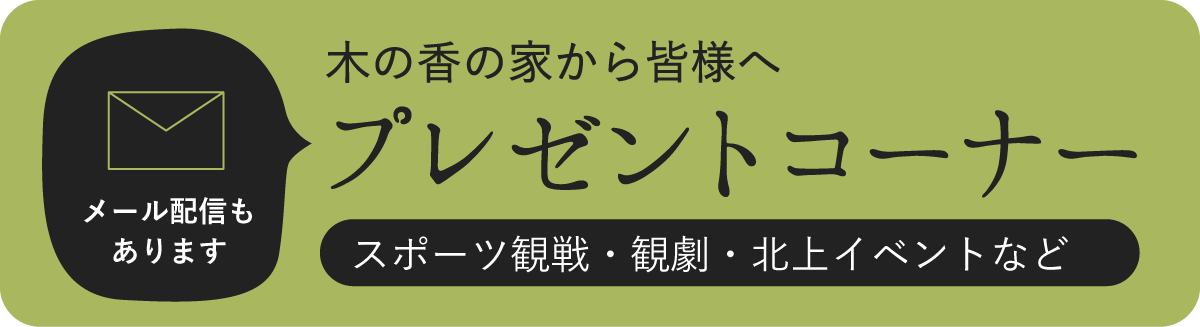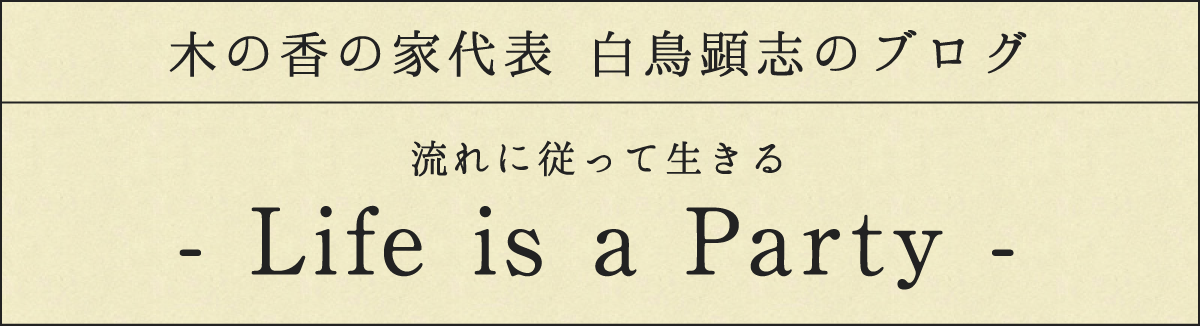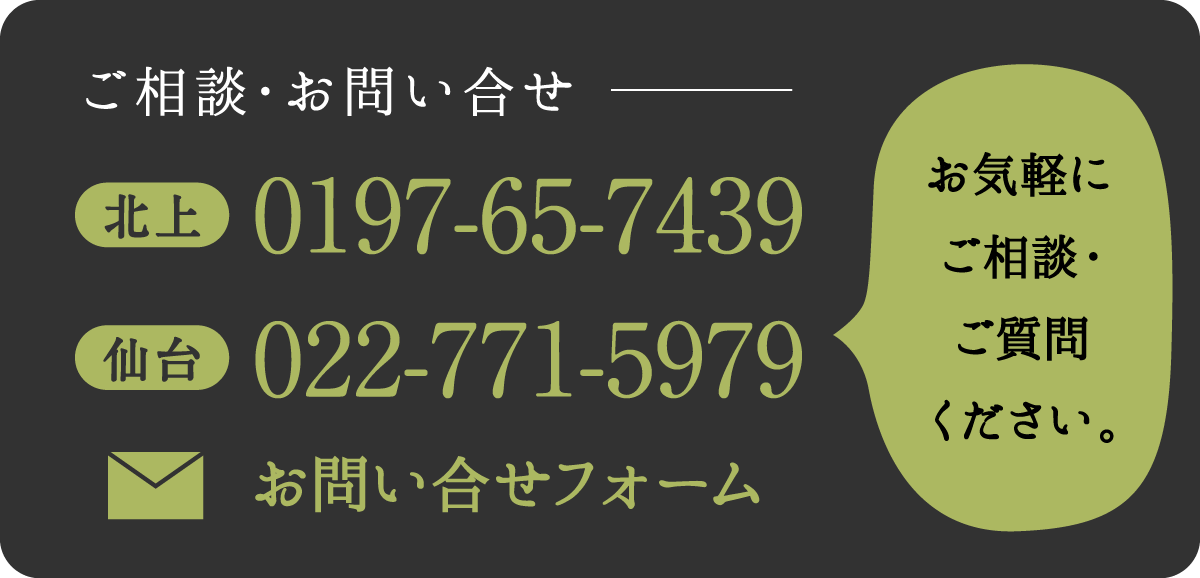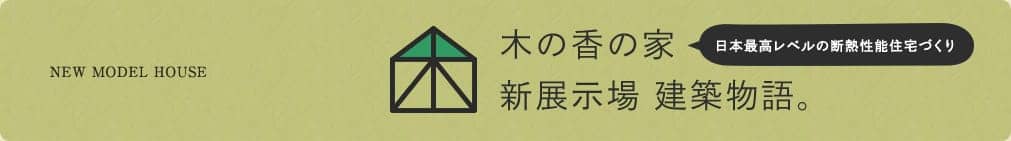
- 北上事務所
- 0197-65-7439
- お問い合わせフォーム
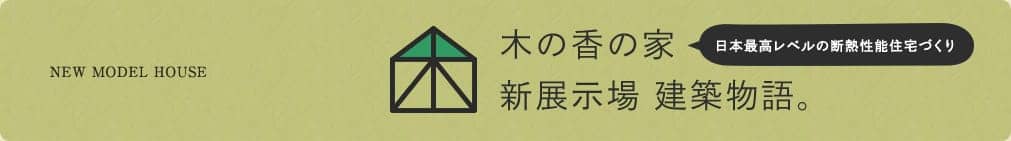
TOP > 木の香の家 新展示場建築物語
【9年目の住宅性能メモ:11月24日・25日・26日】ほぼ毎日0℃
11月下旬
3日続けてほぼ0℃になりました。
ベンチコートも使うようになりました(^^;)
実験ハウスはまだ20℃台をキープしてます。
まだ暖房はスタートしておりません。
9年目でこの性能はうれしいですね。
慣れるとありがたみを忘れますが・・(^^;)



Posted at: 2024.11.26(火)
【9年目の住宅性能メモ:11月19日・20日】
とうとう氷点下です(@@;)
2日続けてほぼ0℃になりました。
最近は、犬の散歩前に外気温を確認するようになってきました(^^;)
実験ハウスはまだ20℃台をキープしてます。
まだ暖房はスタートしておりません。
南側の窓が多いことが、こういう時期は役立ちます(^^)
 11月19日
11月19日
 11月20日:とうとう氷点下
11月20日:とうとう氷点下
Posted at: 2024.11.20(水)
【9年目の住宅性能メモ:11月6日】
外気温1桁の日が増えましたね・・
今朝も外気温6℃台でした。
室温は24℃台です。もちろん暖房は入ってません。
柿の実もすっかり色づきました。
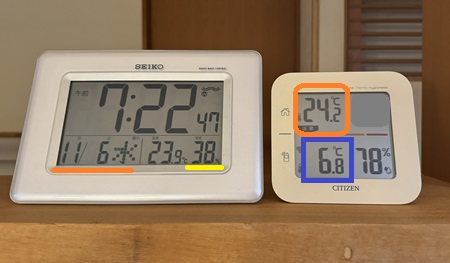

Posted at: 2024.11. 6(水)
【9年目の住宅性能メモ:11月4日】
11月4日...めっちゃ寒いです。
今朝のコロの散歩はめちゃくちゃ寒かったです。。
外気温 2.8℃ ←ついに2℃台...
室温は23.9℃なので本当に気づきません。
(もちろん未だに暖房は使ってません。)
9年目でも性能は十分に維持できてます(^^)。


Posted at: 2024.11. 4(月)
【9年目の住宅性能メモ:11月1日】
11月1日...1桁気温から11月はスタートです。
いつも犬の散歩のときに気づきます。
外気温1桁はやはり寒さを感じますね。
外気温 6.5℃
室温は24.8℃なので本当に気づきません。
(もちろん未だに暖房は使ってません。)
9年目でも性能は十分に維持できてます(^^)。
繊維系の断熱材と『施工方法の工夫』すごさですね。

Posted at: 2024.11. 1(金)
【9年目の住宅性能メモ:10月29日】
10月29日...1週間ぶりに気温がいきなり低くなりました。
いつも犬の散歩のときにびっくりします。
外気温 5.5℃
室温は25.3℃なので本当に気づきません。
(もちろん未だに暖房は使ってません。)
9年目でも性能は十分に維持できてます(^^)。
繊維系の断熱材と『施工方法の工夫』すごさですね。

Posted at: 2024.10.30(水)
【9年目の住宅性能メモ:10月21日】
今朝、コロの散歩をしていたら激寒でした(@@)
家に帰って温度計を見てびっくりです。
とうとう外気温 3.2℃
でも室温は23.3℃です。
9年目でも性能は十分に維持できてます(^^)。
繊維系の断熱材のすごさですね。
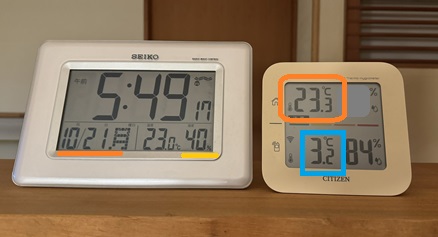

Posted at: 2024.10.21(月)
2月12日【暖房時間...1週間分チャレンジ】
暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。
1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・
2月12日の朝です。
昨日と一昨日は見学会でした。
今年の2月はなんかおかしい・・出来すぎです。
なんと、ここにきて6日続けて「無暖房」で生活できました(^^)。
12月1日~累計暖房時間は...2月11日まで
134時間/168時間(24×7日分) です。
1週間分使ってません・・正直言って、自分でも驚きです。

昨晩7時頃の様子
室温 23.5℃(陽射しのみ)
外気温 1.0℃
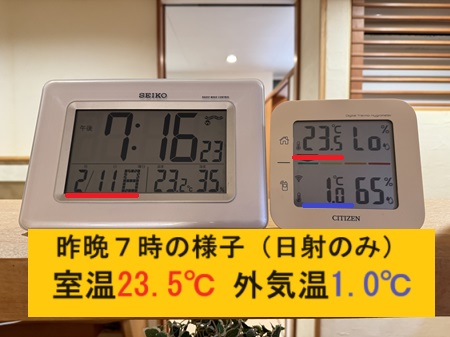
今朝5時の様子
室温 21.4℃
外気温 ー3.8℃
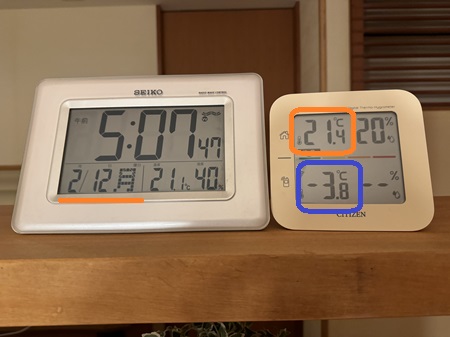
1週間使い切るのは2月のいつになるのか・・気になってきました(^^;)
Posted at: 2024.2.12(月)
2月2日【暖房時間...1週間分チャレンジ】
暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。
1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・
2月2日の朝です。
1月末頃~昨日2月1日まで・・なんと、ここにきて6日続けて「無暖房」で生活できました(^^)。
今年の冬は、出来すぎの天気です!
沿岸や仙台で建てたお客様が暖房時間が少ないのが理解できます。
【中間報告:1月末までの合計】
12月1日~累計暖房時間は...2か月間で
114時間/168時間(24×7日分) です。
1週間分使ってません・・正直言って、自分でも驚きです。

昨日(2月1日)は、本当に『微妙な陽射し』+『寒風の暴風』でした。
帰宅時の室温も微妙で・・暖房つけようか・・と迷うくらい。
かみさんが晩御飯を作って、酒飲んだら、なんとなく暖房要らないね・・と、
せっかくなので・・無暖房で生活しました(^^;
昨晩7時頃の様子
室温 21.1℃(陽射しのみ 微妙な室温)
外気温 -2.9℃
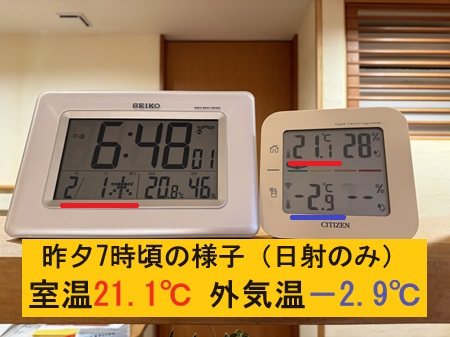
今朝5時の様子
室温 19.3℃
外気温 ー2.3℃
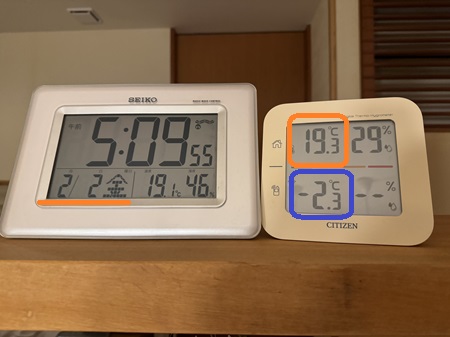
一昨日まで、連続5日の無暖房が続いていたので、すこしやせ我慢(^^;)かな。
でも、晩御飯作って、お酒飲んだら、無理なく過ごせましたので・・
「お!お酒も暖房熱だ(^^)b」
Posted at: 2024.2. 2(金)
1月29日【暖房時間...1週間分チャレンジ】
暖房時間...1週間分チャレンジ】を12月1日~チャレンジ中です。
1週間分(24時間×7日=168時間)の暖房時間を使うのに何日掛かるか・・
1月29日の朝です。
昨日と一昨日は、陽射しがあり、久々に2日続けて「無暖房」で生活できました(^^)。
久々にそういう日があると・・やっぱりうれしいですね!。
昨日!なんと!カモシカが庭に来ました(^^)

12月1日~累計暖房時間は...2日間変わらず
114時間/168時間(24×7日分) です。
今朝の様子
室温 21.1℃
外気温 -2.7℃
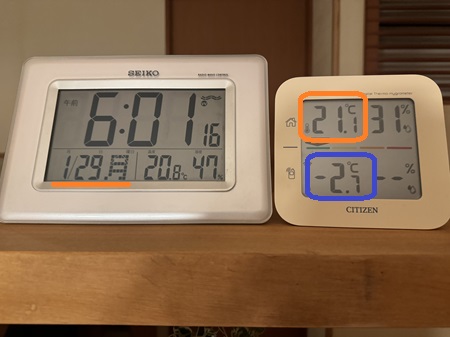
昨夕5時頃(陽射しのみ)
室温 23.0℃
外気温 3.5℃

Posted at: 2024.1.29(月)